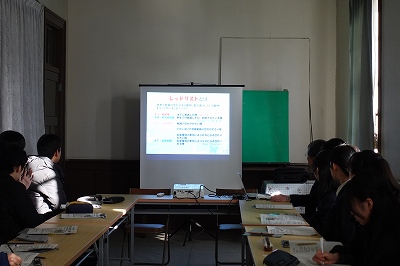令和7年1月25日(土)に博物館研修(高校1年生理数科希望者対象)を行いました。
津山市の「つやま自然のふしぎ館」に希望者20名が訪問し、研修を受けました。はじめにつやま自然のふしぎ館の館長 森本信一氏より、つやま自然のふしぎ館の成り立ちと概要、そして環境保全の重要性についての講義を受けました。
その後、生徒たちは博物館内を見学し、観察・スケッチを行いました。普段はなかなか観ることができない動物の迫力ある姿を間近で観察することができ、生徒たちは熱心にスケッチしていました。
【生徒の感想より】
今回の研修を通じて、生物の多様性を実感でき、環境保全の大切さがわかった。また、館内の動物剥製は皆生きている様に感じた。特に印象に残っている剥製は、シマウマの子どもの剥製で、伏せているような姿勢だったが今にも立ち上がりそうなほどの迫力を感じた。他の剥製にも、他の動物を掴んでいる鳥の剥製や首だけの剥製もあって面白かった。スケッチを通じて動物(イボイノシシ、ヒグマ)の特徴についてより深く理解できた。動物をまじまじと見ることはあまりしてこなかったので新鮮に感じた。
動物の剥製を観察してみて、住む環境に対応するための体のつくりの変化がよくわかった。例えば草食動物のエリトリアディクディクは熱帯のエリトリアの山々で暑さに対応するために鼻が小さく、山で生活する際にバランスを取るために体の後ろのほうが発達していた。草食動物の蹄は丸っぽく走りやすくなっており、毛皮が自然に紛れ込めるように色は茶色ぽく暗めな色になっている。しかし、肉食動物は狩りをするために爪が鋭く、見た目では固く見え、耳は頭頂部にあり、草木に紛れやすい色をしている。人間も環境に応じて進化したこともわかり、生物は絶滅と進化の繰り返しという館長さんのお話もよくわかった。
今回の研修では、展示動物の細部にしっかり注目した観察を行うことができた。体が大きい生物ほど足の構造が平たかったり、寒い地域に住む生物ほど体が大きかったりなど、共通する部分も多くある一方で、なぜこの生物はこれほど体重が重いのか、なぜこれほど鋭い牙や爪を持っているのかわからない生物も多くいた。また、住んでいる地域が遠くなく見た目もほとんど変わらないように見える生物も多くいた。絶滅危惧種も多くいる中で、その内の1種が絶滅したとしても、それが生態系に与える影響を想像することは容易ではないなと思った。しかし、生態系の秩序が、そうした人間の想像することができない複雑な生物同士のつながりによって、保たれているものであることは授業などでも学んでいる。そして、今日、一度絶滅してしまった生物は人間の手で蘇らせることはできない。将来的に復活できたとしても、生態系に与えた損害まで完ぺきに修復することは不可能だと思う。だからこそ、生物多様性の重要性を理解することが必要だ。
この館に展示されている生物の剥製はほとんどが80年以上前に作られているものらしい。観察をしていて、劣化を感じる場面も何度かあった。しかし、ワシントン条約によってもう今後見ることができないであろう貴重生物の剥製を間近に見ることができる場所は県内にも少ない。私がこの館を初めて訪れたのは小学生だったが、当時の衝撃は今でも覚えているし、その時芽生えた生物に対する興味が今でも続いている。そして、今回の研修でも動物たちの生物多様性とその重要性を改めて認識することができる良い経験をさせてくれた。県北地域にこれからも、生物多様性を感じさせ、学ばせてくれるこの貴重な場所がこれからも残り続けてくれたら良いなと思った。これからも生物多様性への理解を深めていきたい。